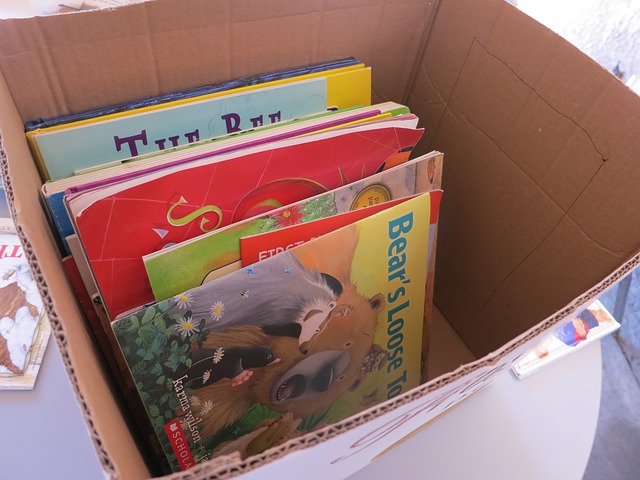休みの日、買い物に出掛けた帰りのこと。
先ほどまでパラパラと雨が降っていたと思っていたら、東の方の空に大きな虹が出ていました。嬉しくなって思わずスマホを取り出してシャッターを押しました。何歳になっても虹を見つけると嬉しくなります♪

目次
七十ニ侯(しちじゅうにこう)では「虹蔵不見」(にじかくれてみえず)
七十ニ侯とは
日本の1年を72に区切って、気象の変化などを短い言葉で表現したもの。
「二十四節気」というものもありますが、これは1年を24に区切り半月ごとの季節の変化を表していますが、これをさらに約5日ごとに区切って細かく表現したものが「七十二侯」です。
虹蔵不見とは
11月22日から11月26日頃の節気。
この頃から、虹が現れる条件が少なくなるためこのように言われる。
これに対するのが、春の清明( 二十四節気) の末侯「虹始見」(にじはじめてあらわる)です。
4月14日から19日頃の節気をいい、春になり虹がくっきりと現れるようになる頃のことをいいます。
冬は虹を見る機会が少なくなる。
そもそも、虹は空気中の水滴に太陽の光があたり反射してできるため、陽の光が弱く空気が乾燥している冬はできにくいと言われています。
冬に虹が現れたとしても、夏の虹のようにくっきりとした虹ではなくぼんやりとした淡い虹になることが多く、短時間で消えてしまうことが多いそうです。

ちょうど今が「虹蔵不見」ということを何かで知っていたということもあり、虹を見つけた時は感慨深いものがありました。 そういえば虹が消えるのも、はやかったような気がします。
冬に虹を見かけたら、もっと喜んでもいいんですね!
「虹始見」までにいくつ虹を見ることができるのでしょうか・・・。
これまで以上に空を見ることが増えそうです♪